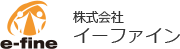解体工事の費用はいくらかかる?費用を抑えるためのポイント

家を解体するタイミングがきたとき、気になるのがやはり「費用」。
でも、解体工事の費用は建物の構造や立地、工事内容によって大きく変わるため、「まずは情報を知ること」が何より大切です。
このコラムでは、解体工事にかかるおおよその費用相場や内訳、費用をできるだけ抑えるためのポイント、さらにスムーズに進めるための事前準備についてご紹介します。
納得して解体工事を進めるために、ぜひ参考にしてください。
解体工事の費用はいくらかかる?費用の目安と内訳をチェック
解体工事を検討するとき、まず知っておきたいのが「どれくらいの費用がかかるのか」ということ。
建物の構造や広さ、立地条件などによって金額は大きく変わりますが、一般的な費用相場を知っておくことで、適正な見積もりかどうかを判断しやすくなります。
【木造住宅解体費用の目安】
・20坪:80万円~100万円
・30坪:120万円~150万円
・40坪:160万円~200万円
【軽量鉄骨造解体費用の目安】
・20坪:120万円~130万円
・30坪:180万円~195万円
・40坪:240万円~260万円
【重量鉄骨造解体費用の目安】
20坪:130万円~140万円
30坪:195万円~210万円
40坪:260万円~280万円
【RC造(鉄筋コンクリート造)解体費用の目安】
20坪:120万円~160万円
30坪:180万円~240万円
40坪:240万円~320万円
【費用の主な内訳】
・解体作業費
建物を取り壊す作業の費用
・廃材の処分費
取り壊した木材やコンクリート、家電などの処分にかかる費用
・養生費
近隣への配慮として設置する防音・防塵シートなどの費用
・重機回送費
重機を現場へ搬入・搬出するための費用
・付帯工事費
ブロック塀やカーポート、樹木、庭石など建物以外の解体にかかる費用
また、建物が密集した住宅街にある場合や、狭小地・高低差のある土地などでは作業の難易度が上がり、追加費用が発生するケースもあります。
正確な費用を知るには、現地調査を伴う見積もりが必須ですが、まずは相場を知っておくことが、解体工事を安心して進める第一歩になります。
解体工事の費用を抑えるためのポイント?
1. 複数の業者から見積もりを取る
費用を抑えるための第一歩は、複数の業者に見積もりを依頼することです。
解体工事の価格は業者によって差があるため、1社だけの見積もりでは本当に適正な価格なのか判断できません。
相見積もりを取るときは、単に金額だけを見るのではなく、以下の点にも注目しましょう
・廃材の処分費が明細化されているか
・追加費用の条件や可能性が明記されているか
・養生シートや近隣対策の費用が含まれているか
・現地調査をきちんと行っているか
見積もりの内容に差がある場合は、業者に理由を確認することも大切です。
内容の透明性や対応の丁寧さも判断基準に加えると安心です。
2. 解体に使える補助金制度を調べる
自治体によっては、老朽危険家屋の除却や空き家対策として解体費用の一部を補助する制度を設けているところがあります。
補助金は申請のタイミングや条件が厳しい場合もあるため、事前に自治体の窓口や公式サイトで確認し、早めに手続きを進めましょう。
補助金には以下のような条件がある場合があるので注意が必要です
・工事前に申請が必要
・建物の構造・築年数・現況などに制限がある
・事前調査や書類提出
3. 付帯工事の範囲を見直す
解体工事には、建物本体の取り壊しだけでなく、ブロック塀・カーポート・庭木・倉庫・浄化槽などの撤去も含まれる場合があります。
これらの「付帯工事」が追加費用の原因になることがあります。
見積もりを依頼する際は、どこまでを解体対象に含めるのかを明確にし、不要な工事が含まれていないかチェックしましょう。
また、残す予定のものがあれば事前に業者に伝えておくと、ムダな工事を避けられます。
解体費用に差が出る、工事金額に影響する6つのポイント
1. 屋根と基礎の大きさ
屋根や建物の基礎部分は、解体に手間がかかり費用もアップします。
たとえば、同じ床面積100㎡でも、平屋と2階建てでは違いがあります。
平屋は100㎡すべてが屋根と基礎にあたりますが、2階建ての場合、1階と2階で50㎡ずつになり、屋根と基礎部分は50㎡分で済むため、2階建ての方が費用を抑えられる傾向にあります。
2. 立地条件と作業のしやすさ
家が建っている場所も、費用に大きく影響します。
重機が入りにくい、隣の家と近すぎる、道幅が狭などの条件があると、作業に手間がかかり、人力作業が増える=費用が高くなる傾向があります。
また、解体後に地面を整える整地作業も必要です。
地盤が弱かったり、木の根や石・アスファルトが多く埋まっていると、追加費用がかかることもあります。
3. 廃材の量と処分方法
建物を解体すると、木材・コンクリート・ガラス・金属など、さまざまな廃材が出ます。これらは「建設リサイクル法」に基づいて種類ごとに分別して処分する必要があり、この分別作業の手間が費用に反映されます。
4. 近隣への配慮が必要な場合
住宅街など、周囲に家が多い場所では、騒音・粉じん・振動などへの対策が必要です。
防音シートや防塵ネットを張ったり、足場を組んだりする手間が増えると、そのぶん費用も上がります。
トラブル防止のためにも、こうした対策は大切ですので、予算に余裕をもって見積もることがポイントです。
5. 壁材・床材に含まれる有害物質
古い建物の場合、アスベストなどの有害物質が使われている可能性があります。
特に昭和40〜50年代に建てられた建物では注意が必要で、アスベストを含む建材が見つかった場合、特別な処理と専門業者による対応が必要になります。
そのぶん費用も上乗せされます。
6. 地中の思わぬ埋設物
解体工事中に、古井戸・コンクリート塊・大きな石など、地中に埋まっていたものが出てくることもあります。
これらの撤去には追加の作業が必要になり、想定外の費用がかかる場合があります。リスクとして頭に入れておくと安心です。
まとめ
解体工事の費用は、建物の構造や立地、廃材の量などによって大きく異なります。
まずは相場や内訳を知り、複数の業者から見積もりを取ることが大切です。
また、自治体の補助金制度を活用したり、不要な付帯工事を見直すことで費用を抑えることも可能です。
さらに、屋根や基礎の構造、アスベストの有無、周囲の環境なども費用に影響します。
正確な見積もりと事前準備で、納得のいく解体工事を進めましょう。